HOME> 解決方法と問題点> 解決方法を選択する
ご病気等により、意思決定が困難なご本人の能力を補完する方法の一つとして、成年後見手続きがあります。
成年後見には法定後見と任意後見があります。
法定後見人手続きとは、
「後見」
「保佐」
「補助」
と3種類あり、申立により家庭裁判所がそれぞれの援助者を選任するもので、それぞれに強力な特徴があります。
任意後見は、ご本人にまだ判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった際に助けてもらう後見人と、助けてもらう具体的内容を事前に決めておき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときに効力が生じる契約です。
成年後見制度には、上記で述べましたように3つの「法定後見」手続きと「任意後見」があり、その中からご本人の財産や日常生活等の保護を図るにはどの手続きが最適なのかを選択することがとても重要なのです。

■ご本人が判断能力を欠く常況にある場合
このような場合は、後見制度を検討します。
広範な代理権・取消権を有する成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、ご本人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為のみすることができ、悪質な訪問販売等から強く保護することができます。

■ご本人の判断能力が著しく不十分な場合
■重要な法律行為についてご本人を保護したい
このような場合は、保佐制度を検討します。
不動産の売買等、民法で定められた重要な法律行為について、「同意権」「取消権」を保佐人に与え、また、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(本人の同意要)。
つまり、後見制度よりもご本人の意思決定の範囲が広くなります。

■判断能力が不十分ではあるが、保佐には至らない軽度の場合
このような場合は、補助制度を検討します。
当事者が申立てた重要な財産上の行為(民法13条)の内、特定の法律行為について、代理権または同意権及び取消権の一方または双方が付与されます。
つまり、保佐よりさらにご本人の意思決定の範囲が広くなります。
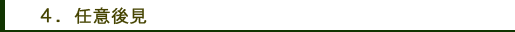
■現在は判断能力はあるが、将来判断能力が不十分になった時に備えたい
このような場合は、任意後見制度を検討します。
ご本人が精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった場合に、生活や療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を予め決めた代理人に行わせるものです。
これは、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
当事務所では、皆様の状況を司法書士が確認させて頂き、
最適なお手続きをご提案させて頂きます。